今の心身の状態に合った
岡崎市の就労移行支援施設がわかる
休みを経ての復帰の第一歩となる就労移行支援施設の利用。
皆さんの今の不安や心と体の状態に合わせて、無理のない利用ができるような施設選びをサポートするサイトです。
休みを経ての復帰の第一歩となる就労移行支援施設の利用。
皆さんの今の不安や心と体の状態に合わせて、無理のない利用ができるような施設選びをサポートするサイトです。
「急いで就職したい」「じっくり準備したい」―あなたの状況に合った施設選びが、新しい一歩を踏み出す鍵です。
下の比較表で、それぞれの特徴とサポート体制を比較検討してください。
まだ就労に不安が
ある方は
VRによるリアルな就労シーンの
練習が何度もできる
就職後も継続したサポートにより、
就職後半年間の定着率は96%※
安心の支援体制をチェック!
短期間での就職を
目指したい方は
半年後に目標を据えた
短期集中コースを用意
随時開催の企業説明会で、
自分に合った就職先を見つけられる
半年での就職成功の仕組みがわかる!
VR(仮想空間)を使って、職場のよくある風景やトラブルなどを体験・練習することができます。
就職した後に起こるであろうトラブルを先回りして何回も練習することによって、何が起こるかわからないという不安感を解消した状態で就労することができます。
スリーエーサポートは就職をゴールではなくスタートだと位置付け、就職後もジョブコーチが継続して相談にのり、職場と連携しながら長く働ける環境づくりを行っていきます。
VRによる事前のシミュレーション、就職後のサポートによって、6ヶ月定着率は96%という高い数字を実現しています。
就職先は従業員数1,000名以上の大手企業から、50名未満の小規模企業まで様々です。
事務、デザイン会社、工場のライン作業、動画編集・撮影業務、清掃業務など、業種や職種に応じて希望に合った職場を見つけてくれます。
AAA supportに通い始めるまで、とにかく不規則な生活をしていたので、ヘトヘトになって続けられないかも、と心配していましたが、特に苦も無く、皆勤賞を頂いた月もあります。
その期間の中で、資格も2つ取ることができ、仕事への気後れも減り、新しい一歩を踏み出す事ができました。
自分もやればできた、という自己肯定感は私にとってとてもプラスになりました。
面接を受けた時、利用空間・スタッフの笑顔も勿論の事、「ここで自分の目標を決めて実現したい!」と思いました。
そして、沢山の助言や訓練・資格も取得する事もでき、就労することができました。
利用者さん・スタッフの皆様、本当に有難うございました。
| 所在地 | 〒444-0874 愛知県岡崎市竜美南1丁目3-1 2F |
| 営業時間 | 10:00~15:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日 |
自己分析を通じて強みや適性を明確にし、短期間での就職を支援。
履歴書や職務経歴書の作成、模擬面接、企業見学などを通じて、実践的なスキルを身につけられます。
また、就職後の定着支援も充実しており、長期的な就労の安定を図ります。全国の企業や支援機関との連携により、一人ひとりに合った職場を見つけることができます。
企業説明会を随時開催しており、気軽に参加することができるので、自分に合った就職先を見つけやすくなります。
個別相談も受け付けているため、利用者のニーズや状況に合わせたアドバイスも可能です。
カリキュラムも豊富に揃えており、就職に関する講義やパソコンスキル、リフレッシュ活動などが含まれ、体調管理システムで自己管理もサポートします。
日本生命保険相互会社、株式会社サイバーエージェントウィル、株式会社ソフマップ、株式会社東京デリカ、日本年金機構、アマゾンジャパン合同会社、株式会社ソフマップ、株式会社東京デリカ、日本年金機構、アマゾンジャパン合同会社、ANA エンジンテクニクス株式会社、株式会社ニチイ学館 など
利用し始めた頃は、「まずは焦らず就職するために必要なスキルを身に着けてから就職活動を始めて、大体1年くらいで決まれば・・・」と思っていました。
ですが、半年という予想より短い期間で就職先が決まりました。
応募書類の確認や模擬面接など事前準備はもちろんありましたが、面接に担当の職員さんが同行してくださったので、安心して受けることができました。
就職活動に悩むこともありましたが、いつでも相談を受けてくれるのも心強かったです。
随時相談を受けてくれるのも心強かったです。
就労前の職場実習を希望していたので機会を作って頂き感謝しています。
応募書類の作成や面接に苦手意識がありましたが、スタッフの方々に何度も丁寧に指導していただいたおかげで不安が減って自信がつきました。
| 所在地 | 〒444-0044 愛知県岡崎市康生通南3-31 第2マルワビル1階102号室 |
| 営業時間 | 月火水木土 10時~16時(開所時間 9時~18時)
金のみ
10時~14時(開所時間 9時~18時) |
| 定休日 | 日曜日 |
ソーシャルスキル訓練とは「挨拶をする」「自分の意見を言う」など、仕事含め社会生活全般に必要な能力を育てることです。
就労支援の現場では、利用者同士によるロールプレイやディスカッションを用いて行われます。
この訓練をVR(仮想空間)を使って行うのが「VRソーシャルスキル訓練」。
VRゴーグルを装着して採用面接や職場などの場面を疑似体験しながら、ソーシャルスキルを効率的に伸ばすことが可能です。
2021年5月時点の、愛知県 岡崎市 周辺で就労移行支援を行っている施設を15社ピックアップしました。
住所や営業時間のほか、各事業所の特徴などを紹介しています。

I T分野への就労が目指せる訓練として、ホームページ制作やグラフィックデザインのスキルを身につけることができます。
キャリアカウンセラーの資格を持つスタッフが利用者の就労をサポートします。
口コミ・評判
作業は大変だけど、やりがいがあって頑張れる

岡崎市が保有する施設の管理運営を行う福祉法人が運営する事業所です。
手厚い職員体制が特徴的で、社会福祉士や管理栄養士、嘱託医などの有資格者と連携した質の高い支援を受けることが可能です。
口コミ・評判
口コミ評判は見つかりませんでした。

企業への就労実績は2021年時点で117名。
発達障害に特化した就労支援プログラムのクラスもあります。
職場実習に力を入れていて、就労定着支援では
ジョブコーチが利用者と就職先企業の双方をしっかりサポートします。
口コミ・評判
利用者さんの個性を尊重されていると感じました。支援員さんの態度がとても良いです。褒めるべきは褒め、然るべき時に注意する、といった感じです。

ジョブコーチによる就労定着サポートやO B交流会の開催など、アフターケアが充実しており、2020年9月時点での就労定着率は96%(就労後6ヵ月定着率)。
V R(仮想空間)を活用した訓練が特徴的で、就労に欠かせないソーシャルスキルトレーニングを楽しく受けることができます。
口コミ・評判
ここに来ていい方向に生活も変わりました。自暴自棄になっていましたが、ここで支援員さん方に出会って通うのが楽しくなりました。働く場所も少し諦めていましたが今では、前から働きたかった場所へ働くことができました。ありがとうございました!

地域に根ざして40年以上の歴史をもつ福祉法人が運営しています。
利用者の得意、不得意な作業をグラフで可視化することで、作業の正確さなどを把握して、利用者に合った職種を提案します。
また、対人関係に不安がある方には認知行動療法など独自のサポートを行っています。
口コミ・評判
口コミ評判は見つかりませんでした。

主に精神障がいを持つ方への支援を得意とし、利用者の家族が集って情報を共有する交流会など、事業所を中心とした「つながり」を重視しています。
ジョブコーチが在籍しており、一人ひとりの求職活動をしっかりサポートします。
口コミ・評判
アットホームな環境。
スタッフの対応が素晴らしい。
成長できる居場所。

事業所オリジナルの「自己分析ワークブック」や動画教材を使った、独自のカリキュラムを実施しています。
利用者が求職活動を始める前に自分の長所や短所、職種の適性をしっかり把握するプログラムに力を入れています。
口コミ・評判
口コミ評判は見つかりませんでした。
2024年2月13日調査時点、無限の公式HPおよび就労移行支援の対応有無は確認できませんでした(※)。詳しくは事業所へ直接ご確認ください。
身体障がい、精神障がい、知的発達、発達障がい、難病をお持ちの方を対象とした事業所として2017年に開設しました。
病気で外出が難しいが就労支援について一度相談したい、という方には専門スタッフによる自宅訪問も実施しています。
口コミ・評判
口コミ評判は見つかりませんでした。

就労移行支援事業所ですが、金銭感覚を身につけることや
労働のやりがいを感じてもらうために工賃の支払いがあります。
老人介護施設や公共施設での実習、陶芸などの自主生産品を販売するなど働くためのスキルを多方面から伸ばします。
口コミ・評判
口コミ評判は見つかりませんでした。

豊田市に住む知的障がいのある子どもの家族が立ち上げた社会福祉法人が運営する、就労支援事業所です。
自主生産品の製作と販売を中心とした実務訓練で、働くことの基礎知識や対人コミュニケーション能力を伸ばすことが可能です。
口コミ・評判
口コミ評判は見つかりませんでした。
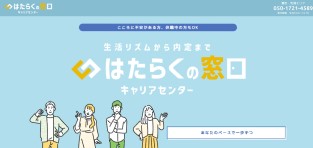
豊田市内に3つの事業所を設けて、精神障がいや発達障がいを持つ方向けの支援をしています。
職場実習で自分の適性を把握し、希望の企業でのインターンで、仕事内容が自分に合っているかどうかを見極めるカリキュラムが特徴となっています。
口コミ・評判
キャリアセンターのカリキュラムで選択理論心理学というのを初めて知って、少しずつではありますが、周りの人と良好な関係が築けるようになって前よりも毎日が楽しく感じられるようになりました。キャリアセンターと出会う前は、何をやるにも気持ちがのらず落ち込んでばかりでしたが、今は好きなことを思いっきり楽しめてます。
利用を迷われている方がいましたら、一度体験してみることをおすすめします。

県立養護学校の生徒保護者有志が、卒業後の子供たちの働く場を作ることを目的に立ち上げた団体が手掛ける事業所。
主に知的障がいを持つ方が利用しています。
カリキュラムでは自主生産品の制作と販売、畑仕事や清掃作業に取り組みます。
口コミ・評判
口コミ評判は見つかりませんでした。

愛知県と岐阜県内で運営される、計5箇所の就労移行支援事業所の一つで、就職実績のある職種は物流や調理など多岐に渡ります。
精神保健福祉士などの有資格者が在籍しているので、心身の相談も気軽に受けられます。
口コミ・評判
僕だけじゃ履歴書書くのに夜通しかかっちゃったんですけど、スタッフのOさんが、修正した方がいいところを書きやすく簡単に説明してくれました。できていないところも何回も教えてくれたんです。全力でサポートしていただいて感謝しています。訓練中もめちゃよくしていただいて。どこって全部です。自分いつも上手くできないんですけど優しくしてもらって、パソコンでも何でも優しく教えてくれました

栄養バランスの取れた無料の昼食提供もあります。
簿記や社会保険労務士など、就職に役立つ資格取得のサポートに力を入れています。
口コミ・評判
子供が今、就労移行で通っています。スタッフさん達は優しく教えてくれています。

愛知県内で20年以上、障がい者の成人向け施設入所や児童の放課後デイサービスなど
幅広い支援事業を行う福祉法人による事業所。
就労に必要な知識についての座学をはじめ、自主生産品の製造と販売を通した訓練があります。
口コミ・評判
口コミ評判は見つかりませんでした。
就労移行支援を利用するには、まず通所可能な就労移行支援事業所を探す必要があります。就労支援事業所は全国で3,000ヶ所以上あり、岡崎市周辺でも20ヶ所以上あります。
この中から自宅から通いやすく、自分にあった訓練が受けられる事業所を選びます。選ぶ際は、見学や体験を利用し、訓練内容や事業所の雰囲気を確認しておくのがおすすめです。事業所によっては説明会やセミナーを開催しているところもあるので、通所を検討している事業所があれば、これらを積極的に利用しましょう。
事業所を選んだら申請を行い、「障害福祉サービス受給者証」を発行してもらいます。申請には障がい者手帳や医師の診断書など障がいがあることを証明する書類が必要で、書類提出後、認定調査と呼ばれる面談が行われます。
認定調査は生活の状況や働く意欲を確認するためのものです。その後「障害福祉サービス受給者証」が発行され、利用開始となります。
就労移行支援を利用するためには、障害福祉サービス受給者証(受給者証)を発行する必要があります。住まい近くの就労支援事業所に出向き、所定の書類を提出し、認定調査という面談を経て、「障害福祉サービス受給者証」が発行されると、就労移行支援が利用できるようになるのです。
なお、よくあるのが「就労移行支援は障害者手帳がないと利用できない」という誤解。就労移行支援に必要なのはあくまでも障害福祉サービス受給者証であり、障害者手帳は必ずしも必須ではありません。ただし後述します通り、障害福祉サービス受給者証を取得するためには病気や障がいを証明できるものが必要となり、そのひとつが障害者手帳になります。つまり、障害者手帳をお持ちの方は就労移行支援を利用でき、お持ちでなくても他の方法で証明ができれば、就労移行支援は利用できるのです。
では、就労移行支援を利用するために必須な障害福祉サービス受給者証とはどんなものなのでしょうか?簡単に言えば、福祉サービスを利用する資格があることを示す許可証あるいは免許証のようなものです。
そもそも就労移行支援は国が行う福祉サービスであり、利用するには明確に定められた条件を満たしている必要があります。つまり、障害福祉サービス受給者証が発行された方は、就労移行支援を利用するための条件をクリアしていると、正式に認められたという証になるのです。
障害福祉サービス受給者証が発行される対象は「病気や障がいにより就労が難しい状況であること」という要件に合致している必要があります。そうした病気や障がいを証明するものとしては、以下のものが挙げられています。
そもそも就労移行支援は国が行う福祉サービスであり、利用するには明確に定められた条件を満たしている必要があります。つまり、障害福祉サービス受給者証が発行された方は、就労移行支援を利用するための条件をクリアしていると、正式に認められたという証になるのです。
就労移行支援は本人、または配偶者の前年度所得に応じて利用料(1割負担)がかかる場合もありますが、9割以上の利用者は無料で利用しています。
具体的には生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯は無料で利用できます。市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)の場合は負担金の上限が月額9,300円、それ以外の世帯では負担金の上限が月額37,200円です。
しかし、その他さまざまな減免要件があるので、正確な利用料金が知りたい方は行政担当課に問い合わせてみることをおすすめします。
就労移行支援を利用できる期間は、最長で24カ月です。24カ月を超えて利用する場合は市区町村に申請し、審査を受けて必要性が認められた場合のみ可能です。就労移行支援における職場定着支援の利用期間は、就労から6ヶ月です。
補助期間や支援期間のある事業を利用する際に最も気になる点の一つに、「期間内に完了しない場合にどうなるのか」という不安があるでしょう。そして今回解説している就労移行支援においては、2年という期限が設けられており、これは一つの施設での話ではなく全ての移行支援における共通の制限とされており、2年以内の就職が求められてしまいます。さらにこの2年という期間は、途中での中断や就職後においても回復するものではなく、「生涯で2年」という認識になります。
では就労移行支援は2年が経過してしまうと無条件で終了してしまうものなのでしょうか。この答えとしてはNOであり、場合によっては1年間の延長を受けられる可能性があります。これは自治体ごとの審査かいなどによって必要ありと判断されたケースに適用されるものであり、「2年では間に合わなかったものの、あと1年あれば就労できるだろう」と思われる場合に延長可と判断される可能性があるものです。
万が一就労移行支援で就職できなかった場合においても就職に対する訓練や活動は就労継続支援の対応に移ることとなりますので、目の前の取り組みや活動にまじめに取り組む姿勢が重要になります。
実際に利用者をサポートしてくれるのは「就労支援員」「生活支援員」「職業指導員」と呼ばれる人たちです。「就労支援員」は就職活動や職場定着の支援、「生活支援員」は健康管理と日常生活のサポート、「職業指導員」は職務に必要な知識や技術等を身に付けるための支援の提供を行います。
この他、就労移行支援事業所の全体管理を行う「管理者」、個別支援計画の作成やサービス全体の管理を行う「サービス管理責任者」が事業所に在籍しています。
就労継続支援は一般就労が難しいと感じている人に就労や生産の機会を提供するものです。一方、就労移行支援は一般就労を希望する人に、必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を提供します。
ちなみにハローワークにかんしては、求職者だけでなく事業主へのサービスも行っている厚生労働省の機関です。
職業紹介・雇用保険・雇用対策などの業務を実施し、就職活動支援も行っていますが、就労移行支援のように安定して就労する上で必要な能力を身につける訓練の提供や、就労に向けた訓練から職場定着のサポートまでしてくれるわけではありません。この点が就労移行支援とは異なります。
就労移行支援は「就労の場」ではなく「就職するための訓練を行う場」としての機能が求められるものであり、一般企業に就職するために必要な知識やスキルを身に着けるための訓練、並びに就職活動に関する支援を行うという目的があります。収入を獲得しながら利用することはできませんが、手厚く就職に対するサポートを受けることができるため、就職活動を落ち着いて進めることが可能です。
就労継続支援A型・B型は、一般企業で就労することが難しい方に対して働く場を提供したり、企業に就職するために必要な知識やスキルを身に着ける場の提供を目的としています。就労移行支援との違いとして、こちらは働くことがメインとなっており、就労のための訓練や就職活動の支援は行っていません。
それぞれの目的・概要を踏まえ、「就労移行支援」は企業への就職のためのトレーニングを行いたい方、「就労継続支援A型」は障がいに対する配慮・支援を受けながら雇用関係を持って働きたい方、「就労継続支援B型」は障がいに対する配慮・支援を受けながら雇用関係がなく働きたい方のための支援とそれぞれ区分されています。
就労移行支援の事業者数と利用者数は年々増加傾向にあります。コロナ感染拡大の影響により2020年以降は数字が落ちていますが、2022年には全国に約3,300箇所(※)もの事業所と、約39,000人(※)の利用者がいる就労移行支援。年度ごとの推移を表にしてみました。
| 年度 | 就労移行支援事務所数 | 就労移行支援の利用者 |
|---|---|---|
| 2012年 | 2,162箇所 | 22,214人 |
| 2014年 | 2,858箇所 | 23,188人 |
| 2016年 | 3,323箇所 | 31,061人 |
| 2018年 | 3,503箇所 | 35,442人 |
| 2020年 | 3,399箇所 | 40,062人 |
| 2022年 | 3,353箇所 | 39,271人 |
※データおよび数字は2023年4月調査時点の情報です。
就労移行支援を提供している事業所や支援サービスの充実に伴い、実際にどれだけの方が就職に成功しているのか、実績としてどれぐらいになっているのでしょうか。ここでは、各機関から公表されているデータをもとに、就労移行支援がもたらす成果についてご紹介します。
まず、就労移行支援が就職に直結する理由として「個別支援計画」の存在が挙げられます。利用者一人ひとりの特性や希望職種を踏まえた計画を立てることで、実際の業務に必要なスキルを段階的に習得できます。
さらに、企業との連携体制も重要なポイントです。支援機関が企業側と連絡を取りながらマッチングを行い、就職後の定着支援までサポートします。加えて、職場実習や体験を通じて業務内容を事前に把握できる仕組みもあり、ミスマッチを防ぐ効果があります。
厚生労働省が調査した2021年のデータによると、就労移行支援を全国で利用している方のうち、就職に至った人の割合は平均56.3%にのぼります。
就労移行支援を利用するメリットにはさまざまなものがあります。どのようなメリットがあるのかを見ていきましょう。
就労移行支援事業所を利用することにより、業務面での対処法などのサポートも得られます。自分が持っている障害を考慮した上でのサポートを受けられるため、仕事に取り組みやすくなるでしょう。
支援や訓練を受けることによって、自分が持つ強みや弱みを知ることができるでしょう。このことにより、採用担当者へどの部分をアピールしたら良いのかという点がわかりますので、自分が必要とする配慮についても説明しやすくなります。
就労移行支援事業所は、利用者がどのような希望を持っているのかを把握した上でプランを立ててくれるという点も特徴です。そのプランに合わせて、就職活動や日常生活上の支援を行ってくれます。
就労移行支援事業所に通う中では、同じように事業所に通う他の利用者と一緒に訓練を受けることになります。このことから、コミュニケーション力が身につきやすいという点もメリットのひとつといえるでしょう。
例えば、パソコン講座やビジネスマナー、ストレスコントロール、作業訓練などさまざまな研修やトレーニングを受けられる点もポイントです。
日常生活上の相談を行うこともできますし、体調管理の指導を受けることができます。一般企業への就職を目指す上では、健康管理能力を身につけることは重要なポイントといえるでしょう。
単に就職を目指すだけではなく、就労支援事業所を利用して就労した場合には、就労定着支援サービスを受けることができます。このサービスでは、就労した後の悩み事の解決など、定着するための支援を行ってもらえます。
家にいる時間が長い人の中には「朝晩逆転の生活を送っている」のように、生活リズムが乱れているケースもあります。そのような方にとって、就労移行支援事務所は生活リズムを整えるチャンスとなるでしょう。決まった時間と曜日に事務所へ通うことで、少しずつ規則正しい生活リズムへと変えられます。また、規則正しい生活は就職活動に役立つだけではなく、健康状態やメンタルなどにも良い影響をもたらします。
障がいや難病、精神的な病気などを抱えている場合、自分と社会との距離を感じやすく、ついネガティブな方向に物事を考えてしまいがちです。
そういった状況では、就労移行支援事業所のドアを開ける、という行動自体が大きな1歩となるでしょう。専門家と相談しながら少しずつ人と触れ合い、周囲とのコミュニケーションや「できる」体験・テクニックを増やすことで、前向きな気持ちになっていくケースも多いようです。
就労移行支援では、企業に対して紹介状や推薦状を書いてくれます。この支援は就職活動のために就労移行支援に通う方だけでなく、採用する企業側とっても「第三者の目線による推薦状」として、安心できる材料になりやすいでしょう。
ハローワークと異なり、就労移行支援事業所で職業訓練を受けられるのは、障がいや病気を抱えた方が対象です。様々な境遇の中で就職へ向けて前向きに活動を行っている人たちと関わるうちに、自分と似た悩みを抱えている人に出会えるかもしれません。
自分の悩みを分かち合える、あるいは理解してもらえるコミュニティを構築できる可能性があります。
さまざまなメリットがある反面、就労移行支援のデメリットとして考えられるのは以下のような点です。
サポート内容はそれぞれの就労移行支援事業所により異なります。そのため、事業所によってはサービスの内容が合っていないと感じることもあるでしょう。また、傾向として障害者枠での就職を目指すケースが多くなっているため、一般枠を希望している場合にもニーズと合っていないと感じる可能性もあります。
利用料は1割負担となっており、前年の世帯収入によって負担上限月額が決まります。この利用料をデメリットとして感じることもあるかもしれません。
短期間でもアルバイトをすると雇用されたとみなされることから、就労支援を受けられなくなるという点もデメリットのひとつです。ただ、自治体や就労移行支援事業所によっては、アルバイトが許可されるケースもありますので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
就労移行支援事業所では、求人紹介を直接行うことができませんので、ハローワークなどと連携して職場を探すサポートを行ってくれます。
全国に約3,300箇所(※)ある就労移行支援事業所ですが、各事務所のサービスが全て同じというわけではありません。施設によって、カリキュラムや支援メニューは異なります。自分が目指したい目標・方向性と違う場合、満足なサービスを受けられなかったり、事務所によっては就職率や職場定着率が低いケースもあります。
就労移行支援事務所の差があるからこそ、「自分の目標に合うプログラムを組んでくれるのか?」「カリキュラム終了後の就職率や職場定着率がどのような数値になっているか」などをチェックして、納得できる事務所選びを行う必要があるでしょう。
合理的配慮とは「一人ひとりが過ごしやすい社会を作るために、お互いに支え合い共に活躍するための環境を調整しよう」という考え方です。発達障がいや障がい者支援という面においては、「日常生活や社会生活を送るうえで困難な部分を、周りのサポートや環境の調整などで軽減する配慮」を意味します。
国内においては、2016年4月1日に「障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行され、行政機関・学校・企業などの事業者に、合理的配慮の提供と障がいを理由にした差別的対応の禁止が求められるようになりました。
また雇用分野においても、2024年4月1日から改正法の施行される「改正障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)」により、事業主の合理的配慮が法的に義務付けされています。
合理的配慮の具体例として、勤務先の入口の段差をスロープ(携帯スロープなどでも可)にする、通勤ラッシュ時の電車通勤が難しい障がい者に対しては通勤ラッシュを避けた出勤時間を設定するなどが挙げられます。
働く企業や事業主に合理的配慮を得るには、どのようなシーンが困難なのかを伝え、理解してもらう必要があります。こちらでは合理的配慮を進める過程を紹介します。
障がいの特性が一人ひとり異なるように、働くうえで困る内容もそれぞれ違います。まず働く場面を実際に想定して、どのような仕事内容・シーンが困難なのかを自分なりに整理することから始めると良いでしょう。
自分で対処できない内容に対しては「どのような配慮があればできるようになるか」といった具体的な解決策を作成・提示すると、よりスムーズな導入が期待できます。
まとめた配慮事項をもとに、合理的配慮の確認と相談を職場に申し出ます。企業側は合理的配慮を提供する義務があるため、業務内容や働く環境でどのような合理的配慮が提供できるかを整理します。
合理的配慮についての話し合いを進めますが、企業は必要とされる全ての配慮を提供しなければならないわけではありません。企業にとって負担になりすぎない範囲、かつ障がいのある人が働きやすい・能力を発揮しやすい方法を、双方の話し合いですりあわせることが大切です。
障がいをもつ人と企業の間で、相互理解を深めながら合理的配慮の検討を行い、最終的にどのような配慮を実施するのか決定します。合理的配慮の実施後に不便があったり、働く環境の変化で内容を変更する必要性が生じたら、随時改善・見直しを行いましょう。
就労移行支援の利用を検討している方にとって、「どう相談すればいいのか」「自分の状況でも利用できるのか」といった疑問を持つことは自然なことです。本項では、就労移行支援を受けるための相談の流れを解説し、よくあるケース別の対応方法についても紹介します。
就労移行支援を受けたいと思ったら、まずはお住まいの地域にある就労移行支援事業所へ直接連絡をしましょう。電話やWebフォームから問い合わせが可能なところが多く、初回相談は無料で行っている事業所も多くあります。不安なことがあっても、事業所の方々が親身に接してサポートしてくれますので、まずは小さなことでも相談してみるところから始めるのはいかがでしょうか。
相談後は、実際に事業所の見学や体験利用ができます。見学では、施設の雰囲気やスタッフの対応、実際のプログラム内容などを確認できます。体験利用では、数日間プログラムに参加することができ、継続利用の判断材料になります。事前に質問をまとめておくと、より有意義な見学・体験となるでしょう。
就労移行支援を正式に利用するためには、市区町村への申請が必要です。申請には障害福祉サービス受給者証が必要で、医師の診断書や意見書が求められることもあります。手続きは事業所スタッフがサポートしてくれる場合が多いため、一人で抱え込まずに相談しましょう。
利用開始後は、個別の支援計画に基づいて、就職に向けた訓練や生活面のサポートが行われます。就職後も定着支援として、職場との橋渡しやフォローアップ面談などを受けることができます。これにより、就職後の不安やトラブルを軽減できます。
長期にわたり休職している方でも、無理なく復職や転職を目指せるサポートがあります。体調に合わせてプログラムの調整も可能ですので、まずは現状を正直に相談することが大切です。
発達特性に配慮したコミュニケーション支援や職場実習が用意されています。就労移行支援施設ではご本人の特性や困りごとを理解してもらえる環境を整えているため、不安な気持ちに寄り添った対応を行っています。
過去に就労経験がない方や、長期間社会との接点がなかった方も対象です。基礎的な生活リズムの整え方から、ビジネスマナー、履歴書の書き方まで、就労までに必要となるものについてサポートしてくれます。
就職後も継続的に支援を受けられる「定着支援」制度があります。人間関係の悩みや業務上の不安などを相談できる体制があるため、就職が決まった後でも定着支援について相談してみてください。
はい、相談だけでもお気軽にご利用いただけます。「まず話だけ聞いてみたい」「就労移行支援ってどんなもの?」といった段階でも歓迎しています。実際に通所するかどうかは、相談のあとにゆっくり検討できます。
多くの方が自己負担なし、または月数千円ほどで利用しています。負担額は前年の所得などに応じて決まるため、詳細は自治体または事業所にご確認ください。
はい、在職中でも条件を満たせば利用可能です。転職を考えている方や、職場に悩みがある方がスムーズな移行を目指して利用するケースもあります。
原則、医師の診断書や意見書があれば申請は可能です。ただし、自治体の判断や追加資料が必要な場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
自己負担額は所得に応じて変わります。ほとんどの方が無料、または月額上限が2,460円〜9,300円程度となっています。
はい、自治体や事業所によって交通費や昼食費の補助制度があります。対象となる条件や金額は地域差があるため、利用前に確認しておきましょう。
一部の事業所では、在宅訓練(リモート支援)に対応しています。体調や通所の難しさに応じて、在宅と通所を組み合わせることも可能です。
原則、利用者の自己負担になります。ただし、教材の一部貸与や助成制度がある事業所もあるため、希望の資格がある場合は事前に確認しましょう。
はい、「定着支援」として就職後のサポートを受けられます。職場への同行や定期面談など、働き続けるための支援が用意されています。
ハローワークは求人紹介が中心なのに対し、就労移行支援では訓練・面接対策・職場定着まで一貫して支援されます。
送迎の有無は事業所によって異なります。身体的に移動が難しい方などに対応しているところもあり、事前確認がおすすめです。
はい、ご本人が来所できない場合でも、家族や支援者だけでの見学・相談が可能です。周囲の方からの情報収集も有効な第一歩になります。
申請から利用開始までは、平均2〜4週間ほどかかります。自治体によって異なるため、早めの準備がおすすめです。
一定の条件を満たせば、最大1年間の延長が認められることもあります。体調や状況に応じて、自治体と相談のうえ決定されます。
はい、希望に応じて一般枠へのチャレンジも可能です。履歴書添削や面接対策なども丁寧に支援してもらえます。
事務・販売・清掃・IT系など、さまざまな企業があります。ご本人の希望やスキルに合わせて、個別にマッチングされます。
はい、健康状態や生活状況に応じて、一時的な休止や後日の再開も可能です。無理なく継続できるよう、柔軟に対応してもらえます。
就職活動の方法によって異なります。障害者雇用枠で就職する場合は伝わりますが、一般雇用枠で就職する場合は、ご本人の同意なしに事業所から企業へ情報が伝わることはありません。就労移行支援事業所は、あなたが安心して働けるよう、伝える範囲を一緒に検討します。
はい、原則として利用可能です。就労移行支援はお住まいの地域に関わらず利用できますが、サービス提供の可否は自治体や事業所の判断によります。まずは通所を希望する事業所に直接相談し、お住まいの自治体への手続きについて確認してみましょう。
就労移行支援の選び方や金額といった基礎知識から就労移行支援を受けるための手続きの流れを解説します。
就労移行支援とは、障がいや難病を持つ方が一般企業に就職するために必要なスキルと知識を身に付けたり、適性に合った職場探しをしたりするためのサポートをする障害福祉サービスのこと。障害者総合支援法によって定められている行政サービスのひとつで、原則として最長2年間まで利用できます。
この就労移行支援は企業への就職や開業を希望し、就労可能と見込まれる18歳から65歳未満で身体障害や精神障害・知的障害・難病を抱えている方を対象としています。
就労移行支援の施設は全国に3,000カ所以上あり、支援カリキュラムや特色は事業所により異なります。事業所内でビジネスマナーや実務訓練を行うだけでなく、企業と提携して職場実習に力を注ぐ事業所などもあります。
就労移行支援を受けたい方は、まずはお住いの市区町村の福祉担当窓口に相談してください。利用したい事業所が決まったら、就労移行支援利用の申請用紙に記入して提出します。この手続きによって障害福祉サービスの「受給者証」が発行されます。この受給者証は国や自治体から訓練等の給付を受けられるという証で、就労移行支援制度を利用する際のサービス内容や支給量などが書かれているものです。
ここからが就労移行支援のスタートで、専門知識を持つスタッフと「個別支援計画」を作成して支援計画に沿ったカリキュラムを実践していきます。
就労移行支援を利用する際の自己負担額は、生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯は負担ゼロ円です。それ以外の方は前年の世帯収入に応じて変動します。
実際に障がいのある方が愛知県内で就職された事例について紹介しています。倉庫での梱包作業を行うピッキングの仕事に就いたKさん、建設業界の企業で書類作成やデータ入力、見積り作成などを行っているSさんなど、就職した先でそれぞれ活躍しているのがわかります。
障がい者を雇用することで、企業側でも従業員の結束力が強まり会社に良い影響をもたらしているというケースが多いようです。詳しくはこちらをご覧ください。
就労移行支援は、65歳未満で一般就労したいと考えている、精神障がい・知的障がい・発達障がい・身体障がいなどの障がいのある方や障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方を利用対象としています。
障がい者手帳の有無にかかわらず、医師の診断や自治体の判断により利用可能です。具体的には、精神障がいでは統合失調症・うつ病・双極性障がい・てんかん・依存症など、発達障害では自閉スペクトラム障がい(ASD)・注意欠如/多動性障がい(ADHD)・学習障がい(LD)など、身体障がいでは視覚障がい・聴覚障がい・言語障がい・肢体不自由などが当てはまります。
就労移行支援は、「生活・体調の安定」→「就職準備」→「職場実習・応募」→「就職後の定着」までを 個別支援計画にもとづいて段階的にサポートします。ここでは代表的な 支援内容(サービス/プログラム)を具体例つきで紹介します。
目標職種に合わせて、必要なスキルを段階的に学びます。
体調・特性に応じた合理的配慮(例:業務量・休憩・座席・指示方法など)を 本人と一緒に具体化。必要に応じて企業側への伝え方もサポートします。
主治医や就労支援機関、家族と情報共有しながら無理のない就職計画を作成。 体調変化時は計画を柔軟に見直します。
原則最長24か月の範囲で、週◯日・午前/午後など無理のない通所ペースを設定。 目標・体調に合わせて計画をアップデートします。
体調や障がいの特性などで通所が難しい場合、就労移行支援は自宅で受けるという方法(在宅訓練)もあります。事業所との連携のもと、電話やオンラインでサポートを受けながら、就職に向けた訓練を進めることが可能です。
岡崎市でも一定の条件を満たすことで利用できる制度があり、自治体窓口や事業所を通じて相談・申請できます。
就労移行支援事業所は、就職を成功させるための大切なパートナーです。しかし、多くの事業所の中からどこを選べばいいか迷ってしまう方も少なくありません。
この記事では、失敗しないために押さえておきたい7つのポイントを解説します。必要なサポート内容や支援スタッフとの相性、就職後の定着支援まで、あなたが納得できる事業所を見つけるためのヒントをご紹介します。
うつ病や気分障害を持つ方は、「朝起きるのがつらい」「集中力が続かない」といった悩みを抱え、就職への一歩を踏み出せないことがあります。岡崎市の就労移行支援では、あなたの心身の状態に合わせたサポートを提供しています。
発達障がいを持つ方は、「コミュニケーションが苦手」「仕事の段取りがうまくいかない」といった課題を抱えている場合があります。就労移行支援では、あなたの特性を強みに変えるための訓練を提供しています。
統合失調症をお持ちの場合、就職活動や職場定着には、症状の安定と継続的な体調管理が不可欠です。岡崎市の就労移行支援では、一人ひとりの状態に合わせた専門的なサポートを提供しています。
在学中から就労移行支援の利用を検討する学生の方が増えています。「卒業後すぐの就職に備えたい」「自分に合った仕事を見つけたい」といった希望を、専門的なプログラムでサポートします。
就労移行支援の利用は、ご本人だけでなく、ご家族にとっても大きな決断です。「どこに相談すればいいのかわからない」「親亡き後の生活が不安」といったご家族ならではの悩みや不安を抱えるケースも少なくありません。岡崎市の就労移行支援では、ご家族の負担を軽減するためのサポートも行っています。
障害者雇用枠だけでなく、一般枠での就職を目指したい方のために、就職活動のプロが徹底的にサポートします。
障害者雇用は、あなたの障がいに理解のある職場で、安心して働くための選択肢です。就労移行支援は、その一歩を踏み出すお手伝いをします。
「面接で自分のことをうまく伝えられるか不安」「何を聞かれるか緊張する」といった面接の悩みは、就職活動の大きな壁です。就労移行支援では、個別指導による徹底した面接対策で、あなたの不安を自信に変えます。
就職した後に「仕事内容が合わなかった」「職場の雰囲気に馴染めない」といったミスマッチを防ぐために、企業実習(インターンシップ)は非常に重要です。岡崎市の就労移行支援では、実習を通じた実践的なサポートに力を入れています。

